ある人が亡くなった時(亡くなった人のことを被相続人と呼びます)、その人の財産に関する一切の権利や義務を引き継ぐことを相続といいます。
相続や遺贈によって財産を取得した場合、その取得した財産にかかる税金を相続税といいます。
*遺贈…法定相続人以外の人が遺言によって財産を取得すること
相続税のしくみ
相続税は相続や遺贈によって取得した相続税が課される財産の合計額から控除できる債務と葬式費用の合計額を差し引いた額(課税遺産総額)が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その超えた部分に対し課税されます。
基礎控除について
相続税には『課税遺産総額が一定額以下なら相続税がかからない』という非課税枠があります。これを基礎控除と呼びます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数*1)
・法定相続人が3人だった場合
3,000万円×(600万円×3)=4,800万円
第一順位 子(子が既に亡くなっていた場合は孫)
第二順位 両親
第三順位 兄弟姉妹
被相続人と血縁関係にある人の中で、相続順位が最も高い人+被相続人の配偶者が法定相続人になります*被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人になります
*1『法定相続人の人数』は相続人の中で相続の放棄をした人がいてもその放棄をなかったものとして数えた相続人の数をいいます。被相続人に養子がいる場合、法定相続人に含める養子の数は実子がいるときは1人(いないときは2人)迄となります。
相続税がかかる財産
- 現金・預貯金
- 有価証券・金融派生商品…株式、国債、先物取引等
- 不動産とその権利…土地、家屋、借地権等
- 各種動産…美術品、貴金属、車等
- 保険金…死亡保険金、損害保険金等
- その他…ゴルフ会員権、著作権等

金銭に評価することのできる全ての財産が、相続税の課税対象財産です。
*日本国内だけではなく国外に所在する財産も課税対象となります
被相続人が亡くなったことにより支払われる生命保険金、死亡退職金などは相続によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
*生命保険、死亡退職金の非課税枠は下記の計算式で計算します
**計算式は同じですが、それぞれ別々に計算します
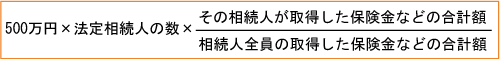
20歳以上の子が60歳以上の父母又は祖父母から生前に財産の贈与を受けたときに、2,500万円迄を特別控除し、父母、祖父母が亡くなったときに相続税で精算する仕組みを相続時精算課税と言います。
相続が発生したときに、相続財産に贈与分を加算します。
相続により財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内に贈与を受けていた場合、その贈与は相続財産とみなされます。
この場合、相続開始の時の金額ではなく、贈与があった時の価格を加算します。
*贈与税の基礎控除(110万円)以下の贈与財産や亡くなった年の贈与財産の価額も加算します
**贈与を受けた際に贈与税がかかっていたら、相続税を計算するときに贈与税相当額が控除されます
相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用
被相続人の借入金や未払い金の他、被相続人が納めなければならなかった税金のうち、未払いのもの等
被相続人の葬儀等にかかった費用の合計額
*墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用、初七日や法事など法要の費用などは葬儀費用には含まれません
主な相続財産の評価方法
それぞれの財産は購入した価格や建築価格(家屋の場合)ではなく、基本的にそれぞれ財産ごとに決められた方法に従って評価額を計算します。
例1:宅地の評価
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります
【路線価方式】
国税庁が定める路線価という数値を使って土地を評価する方法です。路線価地域内に相続した土地がある場合は路線価方式を適用します。
評価額=路線価×補正率×地積
【倍率方式】
固定資産税評価額に規定の倍率(評価倍率)をかけて評価額を算出する方法です。
*倍率方式を利用するのは主に郊外の土地や田畑、山林、原野などです
評価額=固定資産税評価額×評価倍率
*路線価図、評価倍率表は、国税庁のHPから確認することができます https://www.rosenka.nta.go.jp/
例2:建物の評価
評価額=固定資産税評価額×1.0
*建物の評価方法には地域ごとの区分はなく、同一になります
相続税の納税と申告
相続税の申告がある場合、相続の開始があったことを知った日(通常、被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書の提出と納付を行います。*申告書の提出期限に遅れて申告、納付をした場合、原則として加算税及び延滞税がかかります
基礎控除を算出して、相続する財産の課税価格が基礎控除の金額以下の場合は、相続税の申告は不要です。
但し、適用する特例によっては相続税がかからなくても申告が必要になる場合があります。
申告が必要な相続税の主な特例
申告することによりこれらの特例が受けられることがあります。
1.小規模宅地などの特例
被相続人又は被相続人と生計を一つにしていた親族が住居や事業用地として使用していた宅地等が一定の要件を満たす場合、その評価額を一定の割合減額します。
2.配偶者の税額軽減
配偶者の相続する財産が、1億6,000万円以下又は配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
3.寄付金控除
国や特定の公益法人に要件に従って相続財産を寄付することで、寄付した財産について相続税が非課税になります。
4.特定計画山林の特例
5.農地の納税猶予の特例 等
相続税に限らず税金の計算は大変複雑です。上記のように特例を利用することで申告が必要な場合もあれば、申告が不要な特例もあります。よくわからないままにしておくと申告漏れとなりペナルティを課せられる場合も出てきます。その都度専門家に相談することをお奨めします。
また、不動産の評価も幅広い知識と豊富な経験が必要となる分野です。東京国税局の平成29年分のデータによると、相続税の申告をする方のうち、相続財産の約4割が土地や建物の不動産というデータもあり、不動産が相続税に占める割合はかなり大きなものになるのではないでしょうか。
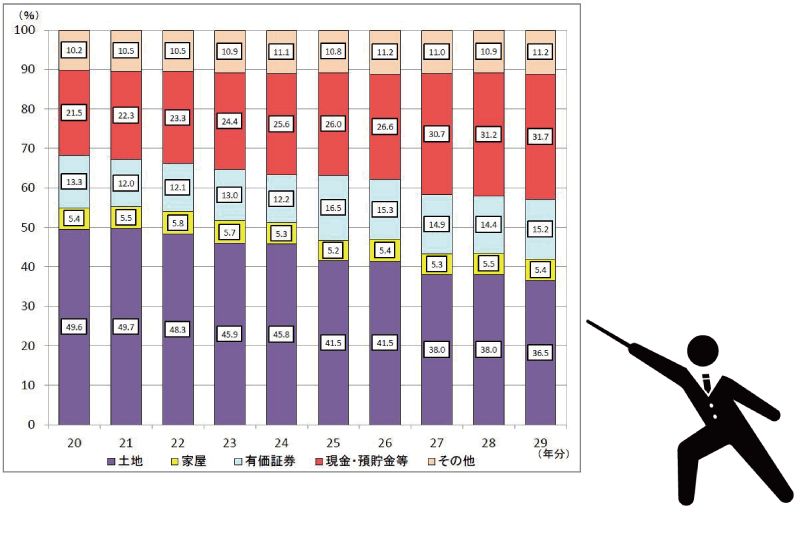
相続税をよく学び、税対策を行うことももちろん大切ですが、相続と掛けて争族とも揶揄される相続トラブルは分割対策の軽視から発生することが大半です。相続税評価額と実勢価格の格差から発生する不公平感も、トラブルの大きな発生要素となります。
不動産の相続税評価額は、あくまでも相続税額を算出するための評価額であり、実際の評価額と大きく隔たりがあることがしばしばです。
弊社では創業50年を超える経験を生かし、簡易的な実勢価格や不動産から見た相続財産の簡易評価、市場の動向アドバイス等のご相談を承っています。所有される不動産の大体の実勢価格を知っておくことで、分割対策の参考にもなります。
ぜひぜひお気軽にお問い合わせください。
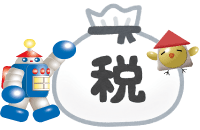
こちらのサイトもご覧ください↓



