不動産に関わる用語としてよく出てくるのが「路線価」という言葉です。
路線価とはどういったものを指すのでしょうか。
路線価とは何か
路線価とは、市街地の道路に沿った土地の1㎡あたりの評価額をいいます。
相続税や贈与税、固定資産税等を算出するときの基準として使われています。
路線価には国税庁が定める相続税路線価と市町村(東京都内特別区(東京23区)は主税局)が定める固定資産税路線価の2つがあり、一般的に“路線価”というと相続税路線価を指します。
国税庁が発表する相続税及び贈与税の基準となる算定評価。毎年1月1日の価格を基準とし、その年の7月初旬に発表されます。
公示地価や実勢価格をもとに定められ、公示価格の8割程度が目安となっています。
固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税などの基準になる路線価。やはり1月1日の価格を基準とし、4月以降に発表されます。
公示地価の7割程度が目安になっています。
*こちらは相続税路線価とは異なり、3年に1回発表されます。地方税の為、各市町村からの発表です。
路線価の定め方
路線価は国土交通省が定める公示地価と実際に売買取引が行われた時の価格である実勢価格を基に決められます。
*公示地価とは…国土交通省が地価公示法という法律に基づいて取引価格の目安として毎年発表しているものです
2020年の発表で日本一高額な路線価になったのは、東京銀座の鳩居堂前で一坪4,590万円。(*一坪は約3.3㎡。畳2畳分くらいです。)
この場所は35年間首位独走中!!さらに4年連続で最高額を更新し続けているそうです。
*相続税・贈与税を計算する際は、それらが発生した年の路線価を使います。例えば、相続または贈与が1月にあった場合、その年の路線価が発表される7月まで待ってから計算することになります
路線価の見方
路線価は国税庁のHPにある路線価図で見ることができます。
*国税庁のHPでは最新の路線価が確認できます
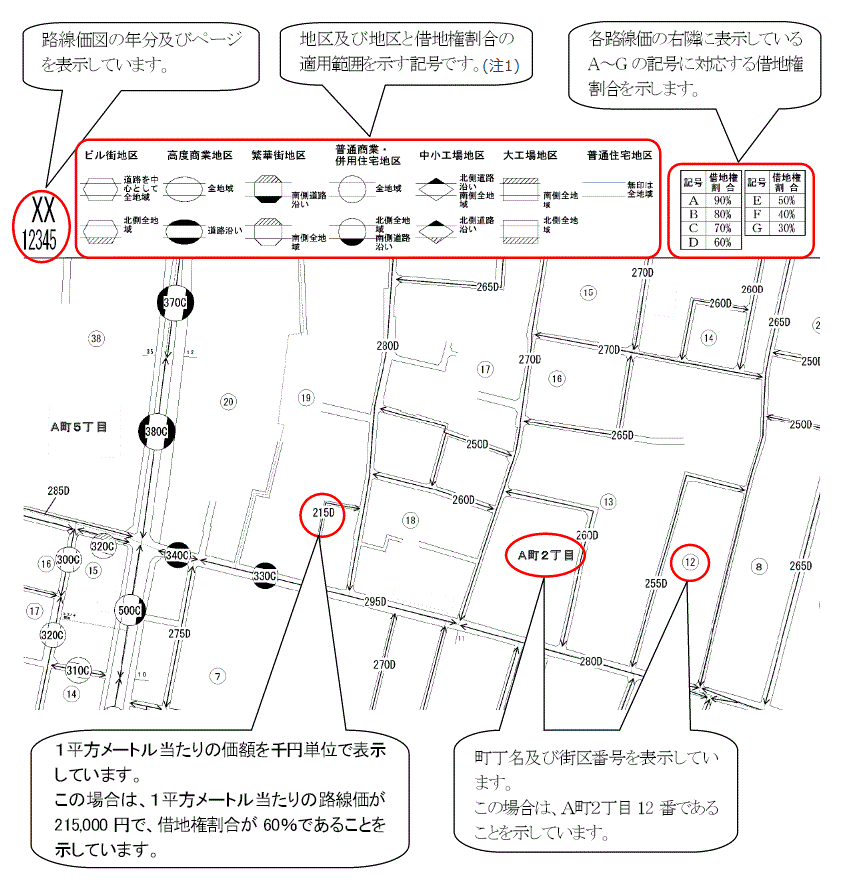
「黒塗り」の場合、その地区区分は「黒塗り」側の路線の道路沿いのみが該当します。「斜線」の場合、その地区区分は「斜線」側の路線には該当しません。
「黒塗り」又は「斜線」ではない「白抜き」の場合、その地区区分はその路線全域に該当します。
国税庁HP 路線価図サンプル https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_prcf.htm
路線価が定められている土地では、土地の相続税や贈与税の計算をするときに路線価を使って算出します。(路線価方式)
*路線価が定められてない土地の場合は、土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する方法を使います(倍率方式)
また、路線価は公示地価の8割程度を目安として定められているので、路線価を0.8で割り戻す(路線価÷0.8)ことで公示地価の水準に修正し、土地の価格の目安と考えることもできます。
ただこの金額はあくまでも税金を算出するための目安。土地の時価(取引価格、適正価格)は土地の形、接道等の状況、周辺環境といった土地固有の条件や市場の状況等で大きく変わります。
時価を知るには、不動産業者に査定を依頼するのが一番と思います。
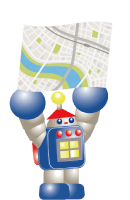
こちらもご覧ください↓
- 国税庁HP『路線価図・評価倍率表』: https://www.rosenka.nta.go.jp/



